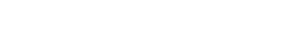生産・製品production/products
かき部門 [給分浜工場]
![めかぶ部門 [大原浜工場]](images/kaki_main.jpg)

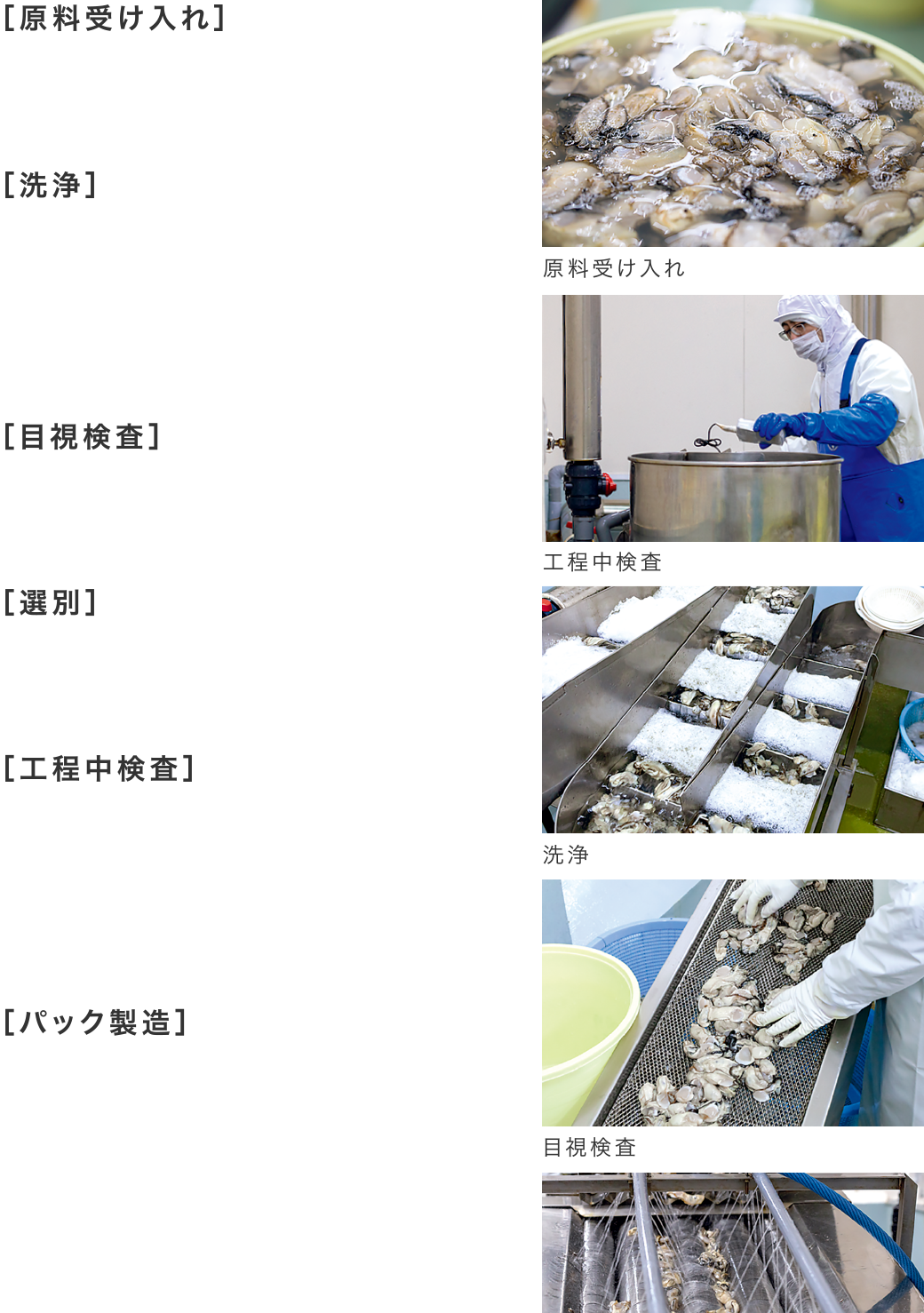
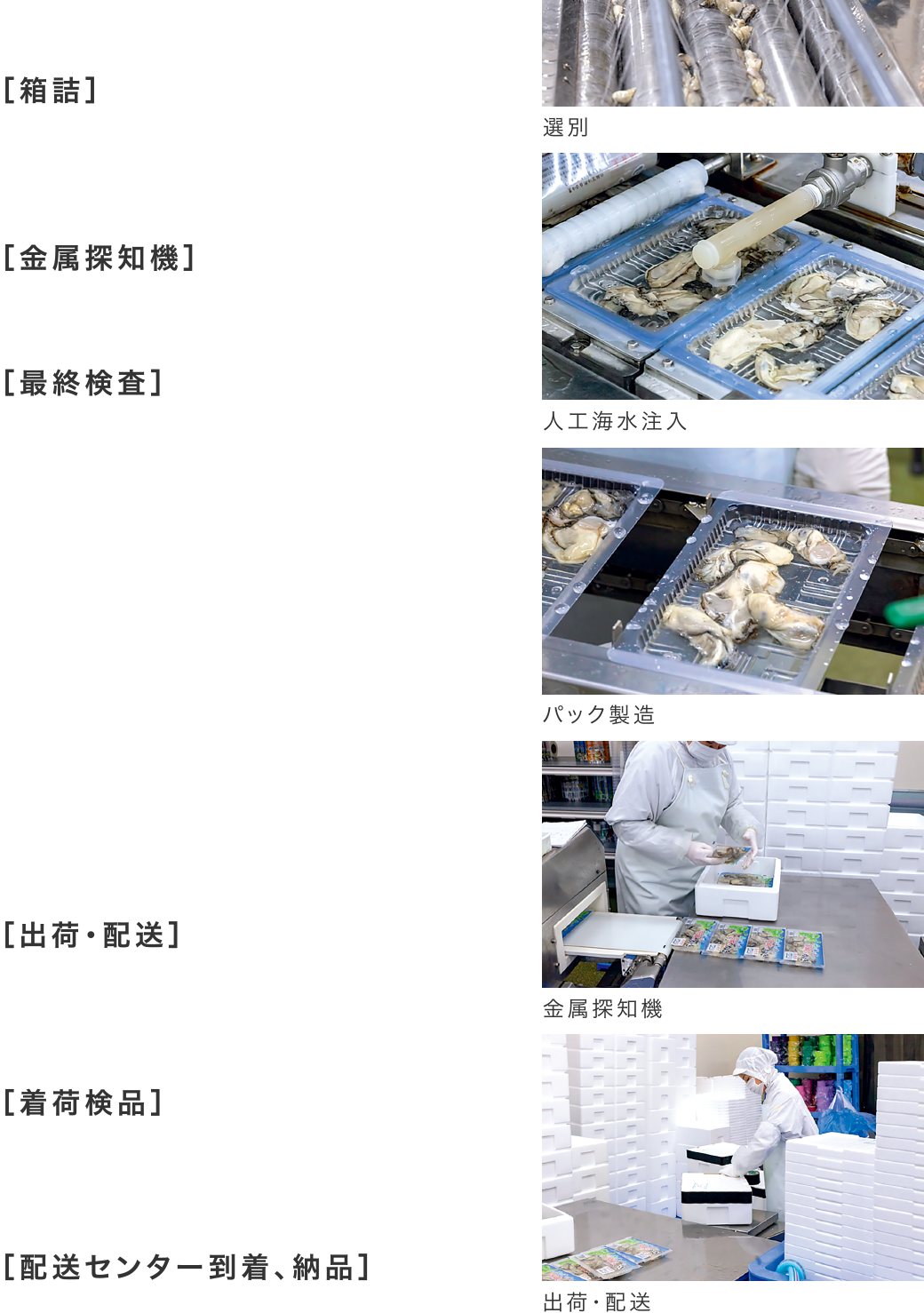
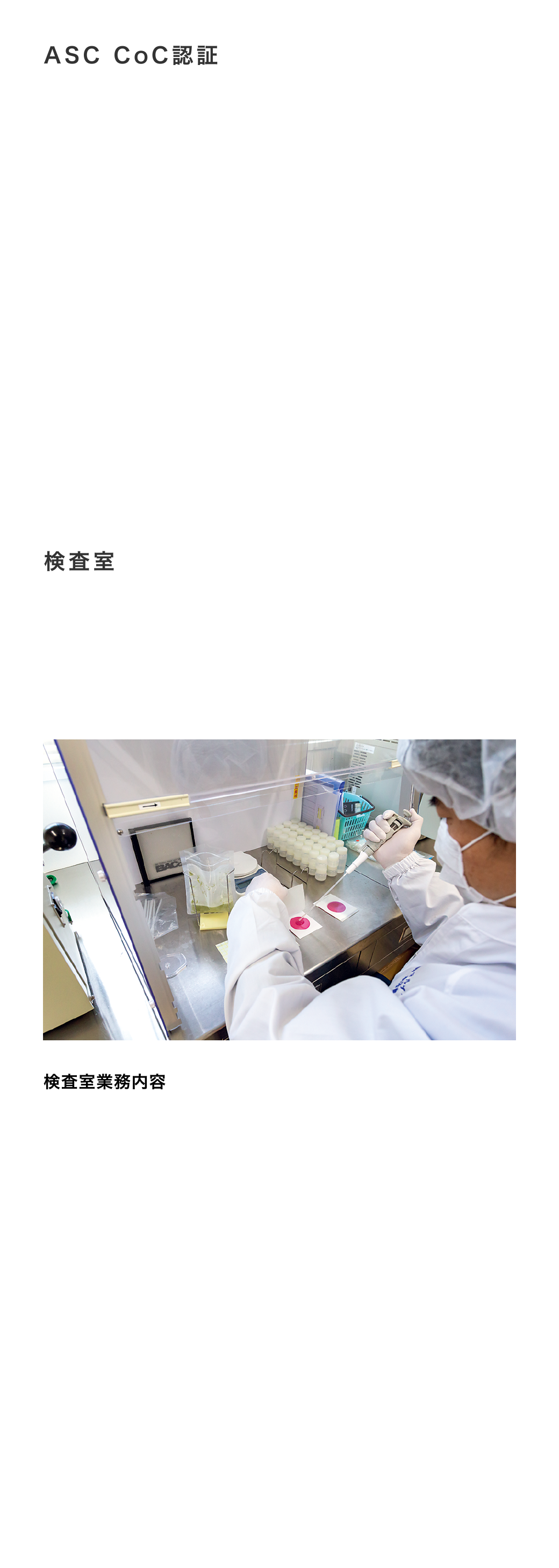
![めかぶ部門 [大原浜工場]](../images/production_mekabu.jpg)
めかぶ部門 [大原浜工場]
健康志向の高まりを受け、ヘルシーな「海の野菜」として注目されるめかぶ。水溶性食物繊維やミネラル・フコイダンが豊富で、健康にも美容にも良いという人気の食品です。
当社のめかぶ部門は、大原浜の漁港にほど近い高台にある新工場(竣工2017年)で加工製造を行っています。
2000坪の敷地に建つ500坪の工場には最新設備が調い、その生産キャパシティを存分に活かして1日あたり3〜4トンのめかぶ製品を加工製造しています。